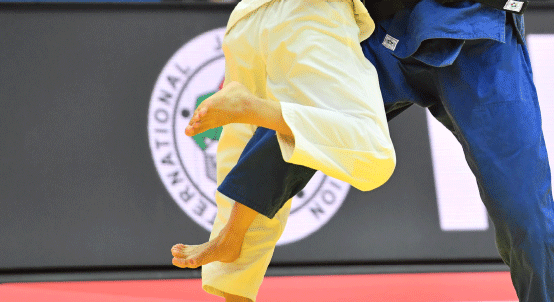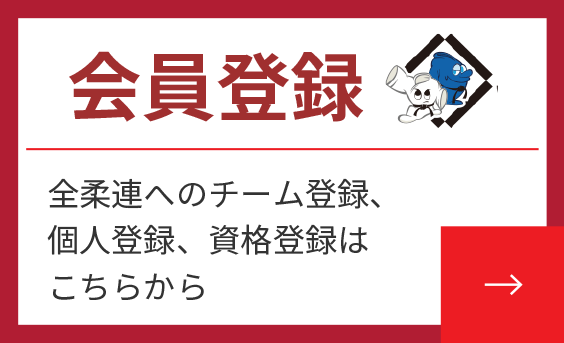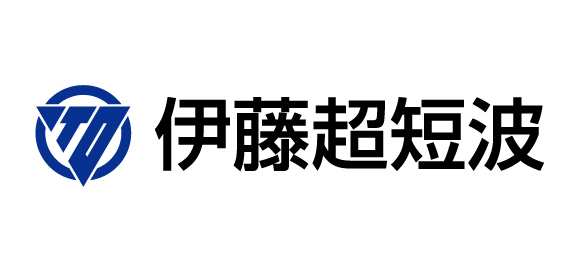審判になるには

全日本柔道連盟が公認する柔道審判員として、Sライセンス審判員、Aライセンス審判員、Bライセンス審判員、Cライセンス審判員の4つの資格があります。
Sライセンス審判員特に技能が優秀であり、本連盟が主催、主管する全国的大会の審判員となる資格を有する者
Aライセンス審判員本連盟が主催、主管する全国的大会の審判員となる資格を有する者
Bライセンス審判員地区柔道連盟(連合会・協会)が主催、主管する大会の審判員となる資格を有する者
Cライセンス審判員都道府県柔道連盟(協会)およびその加盟団体が主催、主管する大会の審判員となる資格を有する者
公認審判員規程(別表1)
2024年4月1日改正
| Sライセンス | Aライセンス | Bライセンス | Cライセンス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ⑴受験資格 | ①年齢 ※1 |
30歳以上 56歳以下 |
23歳以上 54歳以下 |
20歳以上 | 18歳以上 |
| ②段位 | 15年以上、 4段以上 (女子3段以上) |
4段以上 (女子3段以上) |
3段以上 | 2段以上※3 | |
| ③審判経験 | Sライセンス候補者※2当該年度の本連盟登録(個人登録及びAライセンス審判員資格登録)をしている者で全日本柔道連盟審判委員会選考審査部会より認定を受けた後、Sライセンス審査対象大会において2年間の審判経験(実技審査を実施)が必要 | 当該年度の本連盟登録(個人登録及びBライセンス審判員資格登録)をしている者で「B」取得後3年以上の審判経験を有し、その者が本連盟登録した都道府県より推薦を受けた者とする。 | 当該年度の本連盟登録(個人登録及びCライセンス審判員資格登録)をしている者で「C」取得後2年以上の審判経験を有し、その者が本連盟登録した都道府県より推薦を受けた者とする。 | 当該年度の本連盟登録をしている者 | |
| ⑵試験方法及び試験内容 | 実技審査を行い、本連盟審判委員会選考審査部会において審議・認定する。 本連盟審判委員会選考審査部会で定める対象大会において審査する。 |
養成講習会を受講し、学科試験と全日本柔道連盟が指定した大会において実技審査を行う。 受験回数は年1回とする。 本連盟審判委員会選考審査部会から指名された試験官3名以上がこれにあたる。試験官は審判委員会選考審査部会委員、審判委員会委員、Sライセンス審判員の中から指名される。 |
養成講習会を受講し、学科試験と地区柔道連盟(連合会・協会)が指定した大会等において実技審査を行う。 地区柔道連盟(連合会・協会)から選ばれた審査員がこれにあたる。 試験官はAライセンス保持者以上、現行の試合審判規程に詳しい者がその任にあたる。 |
養成講習会を受講し、学科試験と実技試験を行う。 都道府県柔道連盟(協会)から選ばれた審査員がこれにあたる。 試験官はAライセンス保持者以上、現行の試合審判規程に詳しい者がその任にあたる。 |
|
※1:年齢は、Sは推薦時、A~Cは資格認定当日の年齢とする。
※2:Sライセンス候補者*)の選定の手順
※3:既にCライセンス審判員資格を取得している者で初段の者は、2026年3月31日までに2段を取得しなければ資格が失
効する。
①都道府県柔道連盟(協会)が、下記要件を満たす審判員をSライセンス第1次候補者として選定し、推薦書にその旨の詳
細を明記した上で地区柔道連盟に推薦する。
(ア)公認審判員制度運用規則別表2「実技審査ライセンス要件」の評価項目について、Sライセンスの基準全てを満たして
いると判断され、かつ、
(イ)Sライセンス受験資格要件を満たしたAライセンス資格者のうち特に優れている審判員
②地区柔道連盟(協会)は、当該都道府県柔道連盟(協会)から推薦された候補者を地区柔道連盟(協会)が指定した大会の審
判員として参加させた上で、公認審判員制度運用規則別表2「実技審査ライセンス要件」の評価項目に則し、当該候補者の
審判技量を客観的に評価しなければならない。また、評価順位を明らかにした上で、該当都道府県柔道連盟(地区)からの推
薦書の写し及び評価書とともに本連盟審判委員会へ報告する。
③選考審査部会は、地区柔道連盟からの報告をもとに厳正な審議を重ねた上で当該Sライセンス候補者の認定を行うことと
する。