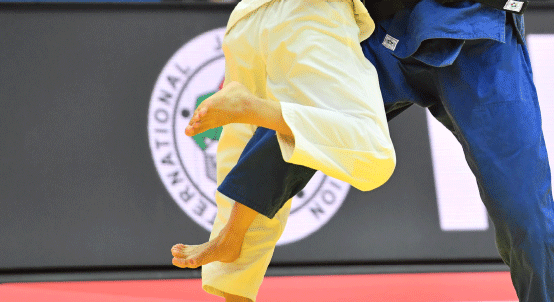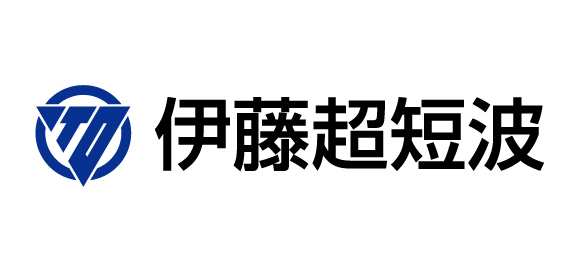プロフィール
向井 理子(むかい りこ)1992年 長崎県生まれ
国士舘大学 専任職員
講道館柔道女子四段
主な活動
2015年~現在 国士舘大学柔道部(女子)コーチ
主な戦績
2005年 長崎県中学校総合体育大会 63㎏級 優勝(中学1年生時)
2006年 長崎県中学校総合体育大会 63㎏級 優勝(中学2年生時)
2007年 長崎県中学校総合体育大会 63㎏級 優勝(中学3年生時)
はじめまして、国士舘大学の向井理子と申します。
この度、瀬戸口栞南さんよりバトンを受け取り執筆の機会をいただきました。栞南さんとは、長崎県長崎市内にある諏訪ノ森柔道教室出身、緑が丘中学出身という共通点があります。また、この春から大学でコーチをされているとのことで、また一つ共通点が増えました。
私は、9歳(小学3年生)の夏に諏訪ノ森柔道教室で柔道を始めました。中学、高校も柔道を続け、2011年に国士舘大学へ入学しました。卒業後は国士舘大学の職員として働いています。また、柔道部のコーチとしても活動しており、監督やコーチ陣と共に日々の稽古やトレーニングの指導に励んでいます。
特に何の功績もない私がこのリレーコラムに参加できるとは夢にも思ってもいなかったので、何を書けばいいのか悩みに悩んだ結果・・・「続けること」をテーマに、私が「尊敬している人」について書くことにしました。
その人は、全日本柔道連盟に所属し、今やIJFスタッフとしても活躍している寺下浩陽さんです。寺下さん(以下「先輩」)は一つ上の学年で、小学生の頃からの幼馴染になります。中学生の頃、県の強化合宿時、路面電車(長崎ではチンチン電車という)での移動中、「降りる」のボタンを私が特に意識せず押したのですが、鉄道の通っていない地域で生まれ育った先輩は、乗った経験の少ない路面電車で「降りる」ボタンをよほど押したかったのか、中学生にもなって悔しそうにしていたのを覚えています。
なぜ、悔しそうにしていた先輩を「尊敬している人」として挙げたのか。それは、「柔道を続ける」という概念を考え直すきっかけを与えてくれたのが先輩だったからです。私は柔道を始めてからずっと、「柔道を続ける」ということは競技者として「勝つこと」だと思い込んでいました。しかし、大学生になって、主務の役職を与えられた私は、学生連盟の事務所に行くことが多かったので、当時、学生連盟で活動していた先輩が同年代の大学生と大会実施に向けて準備をしている光景をよく目にしていました。同年代の人たちが日本武道館で開催される学生大会を主となって運営していると知ったときは衝撃的でした。表舞台には出ないけど「柔道界に必要不可欠な縁の下の力持ち」だと思いました。同時に、「柔道を続ける」のは、競技者だけでなく、大会運営をする人、指導者、審判員、様々なかたちがあること、そして、その活動を各々が続けているからこそ、柔道という競技が成り立っているということを改めて考えることができました。
大学卒業後は、先輩の影響もあってか、東京オリンピックのボランティアに参加したり、全日本大会や日本で開催される国際大会の社会人係員をしたり、指導者ライセンスや審判ライセンスを取得したり、私なりの柔道の続け方をしています。
この考え方やたくさんの貴重な経験は、柔道部の指導者としてはもちろんのこと、大学職員としての業務にも活かすることができています。
それぞれの「柔道の続け方」があるからこそ、柔道の魅力が発揮されると思います!!
次にバトンを渡すのは、私の地元長崎で私の父と一緒に4年半の間、小中学生の指導をしてくれていた田中季香さんです。私が長崎に帰省した際、道場へ行くと、生徒と一緒に明るく楽しく時々厳しく指導していた姿は、とてもフレッシュで活き活きしていました。指導者として「柔道を続けている」一人です!
最後まで読んでいただきありがとうございました。これからも微力ながらたくさんの経験をさせてくれた柔道界に貢献できるよう、柔道を続けていきたいと思います。
ありがとうございました。
- 柔道部で山内監督の誕生日祝いをした時の写真
- 東京オリンピック時、寺下さんとの写真
- 皇后盃の時、寺下さんとの写真
- グランドスラム東京係員の集合写真
- YAWARA Challenge Tournament時、審判員集合写真
※女子柔道の振興ページではJJ Voiceコラムのバックナンバーをはじめ様々な情報を掲載しています。
こちらから是非ご覧ください。